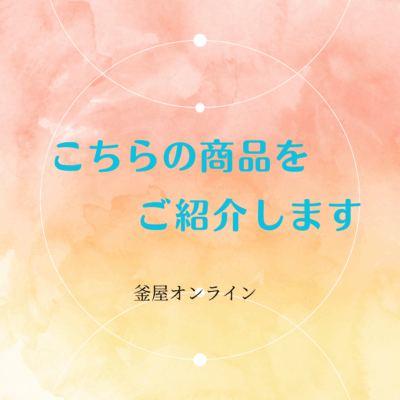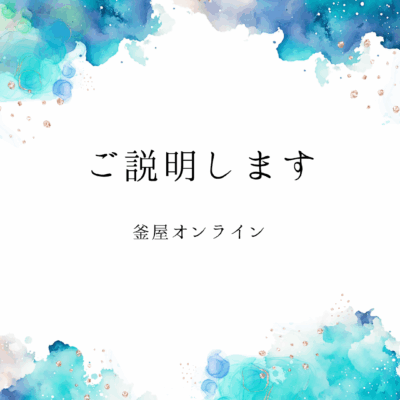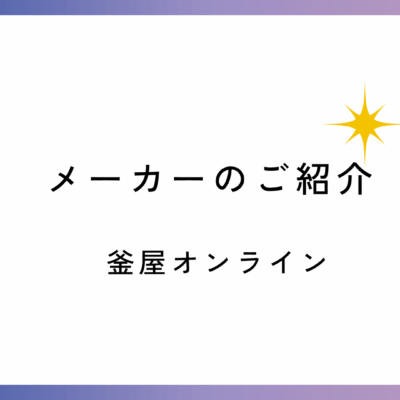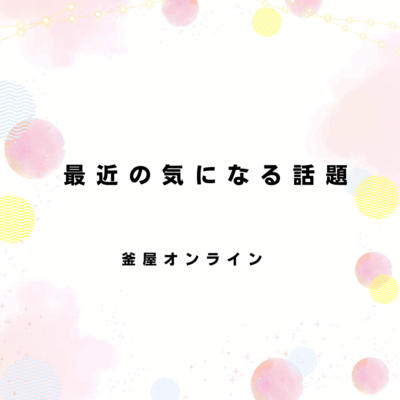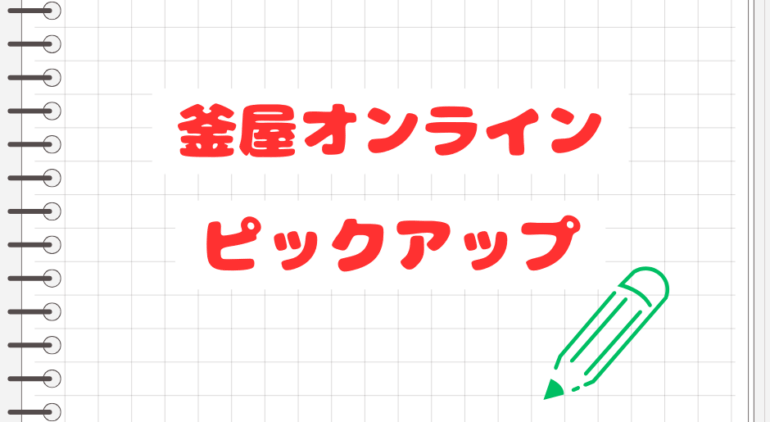
今なぜBCPが求められるのか? 釜屋オンライン
1. BCPとは/なぜ今、中小企業が取り組むべきか
■ BCPの定義
BCPとは、「企業が自然災害・火災・事故・感染症などの緊急事態(あるいは突発的な事故)に遭遇したときに、事業資産の損害を最小限にしながら、中核となる事業を継続または早期復旧できるよう、平常時からの体制・手順をあらかじめ整えておく計画」です。 chusho.meti.go.jp+2chusho.meti.go.jp+2
■ 中小企業が備えるべき理由
- 日本は自然災害リスクが高く、大規模災害だけでなく取引先・サプライチェーンの途絶も含めて事業継続の脅威となっています。
- 大手企業ほどではありませんが、中小企業でも「災害・事故で操業停止→取引先離脱→廃業」という事例が少なくありません。BCP未整備であることが競争力・取引力を弱める可能性があります。
- 実際、国内の中小企業でBCPを策定済・検討中を含めても約半数弱というデータがあります。策定率が低いため、取り組むことで差別化の機会ともなります。
■ 大手企業が中小企業の取引先に求めている視点
- サプライチェーンの脆弱性を低くするため、自社が被災しなくても取引先・仕入先が被災することで供給が止まるリスクを回避したい。特に製造業では「中小企業が取引を継続できるか」という観点が重要です。
- 「災害時も対応できます」という取引の信頼性・継続性を示せる中小企業を優先・選定する傾向があります。
- そのため、中小企業としては取引維持・拡大を狙う上でも、BCP策定・対策は“取引条件”の一つになってきています。
2. 中小企業向け:BCPの具体的な方法論
中小企業の特徴(人員少、設備集中、資金・時間制約あり)を踏まえた、現実的で実効性あるステップを以下に整理します。
■ ステップ0:準備・方針策定
- 経営トップが「何を守る(どの事業が中核か)」「どのように守るか」を表明し、推進体制(担当者・チーム)を決める。
- まずは「中核事業(売上/取引先/地域など事業継続性に直結)」を明確にする。
■ ステップ1:リスク・被害想定
- 自社・自社拠点・サプライチェーンにおけるリスクを洗い出す(地震・風水害・火災・機械故障・感染症・物流寸断など)
- 想定される被害内容(人員・設備・仕入・物流・システム停止など)とその影響を整理。例えば「主要な仕入先が被災したら何日分の在庫で対応できるか」など。
■ ステップ2:重要業務の特定/復旧優先順位設定
- 中核事業を継続するために “最低限止めてはならない業務” を特定。例えば「主要顧客の納入」「基幹設備の稼働」「受注処理」など。
- 各業務について「目標復旧時間(RTO: Recovery Time Objective)」「目標復旧水準(サービスレベル)など」を設定します。
■ ステップ3:代替策・復旧策の検討
- 人員代替、拠点代替、設備・システムの冗長化・バックアップ、仕入・物流ルートの複数化、在庫確保など。
- 取引先・協力会社との相互扶助・共有体制も視野に。
■ ステップ4:実行・訓練/見直し
- 作成した計画を平時から運用可能な仕組みにし、定期的な訓練・演習を実施する。
- 新たな設備や取引など、変化があった場合にはBCPを見直すサイクルを。
■ ポイントとなる「簡易でも始められる対策」
- 生命・安全対策:従業員の安否確認手順・避難・点検。
- 情報共有・バックアップ:図面・設計データ・受注データ・仕入データのクラウド化または遠隔保管。
- 仕入・物流ルートの見直し:主要仕入先/物流業者が被災した場合の代替手段を確認。
- 要員・技能多能化:特定の人しかできない作業が滞るリスクを減らす。
- 資金・流動性対策:突然の停止でもキャッシュフローが維持できるような準備。
■ 補助・認定制度の活用
- 事業継続力強化計画(ジギョケイ)という制度があり、認定を受けることで税制優遇や補助金活用可能となるケースがあります。
- 自治体・商工会議所などが中小企業向けにBCP策定支援を行っている場合もあります。
3. 大手企業が取引先中小企業に求めるBCP対策ポイント
- 大手は「被災によってサプライチェーンが止まる」ことを重大リスクとして捉えており、取引先にも一定のBCP体制を求める傾向にあります。
- 中小企業としては以下のような視点を意識すると、取引継続や新たな取引獲得につながります。
- 文書化されたBCP計画の有無:「いつ何をどうするか」が明文化されているか。
- 業務の優先順位・復旧目標の設定:中核業務が明確で、被災時の対応・復旧手順が定まっているか。
- 代替手段の確保:仕入ルート・物流・バックアップシステム・人材代替などが検討されているか。
- 訓練・見直しを行っているか:計画を作って終わりでなく、実効性を高める訓練サイクルがあるか。
- 透明性・取引先への説明能力:自社のBCPを取引先に説明できる体制があると信頼性が高まる。
- これらを整えることで、単に「災害時対応」の備えというだけでなく、取引先からの信用力・競争力を高める「差別化要素」になります。
4. 未来に向けて:BCPを“守り”から“攻め”に変える視点
- 従来の 「災害が起きたときにどうするか」 という受動的な備えから、
→ 「日常業務を強くする」「変化・リスクに強い事業体質をつくる」 という能動的視点へ移行することが重要です。 - 具体的には:
- 業務プロセスの冗長性・代替性を持たせる。
- DX・デジタル化(例えばクラウドでのデータ管理、遠隔勤務、スマート工場)を進め、災害時だけでなく市場変化にも強くなる。
- 取引先・地域・サプライチェーンとの連携強化:中小企業が地域・業界の“強靱化”の一翼を担うという視点。
- ESG・サステナビリティの観点でも、事業継続力・リスク対応力を整えることが企業価値向上につながる。
- 結果として、BCPを「災害時の保険」ではなく、「経営持続・競争優位を支える構え」として位置付けられます。
5. 中小製造業(御社のような機械部門を抱える会社)向け“すぐできる”チェックリスト
- 中核事業を一つ書き出す:例えば「機械装置の設計・製造・納入」
- 主要な仕入先・外注先を3社書き出す。被災時代替可否を確認する。
- 受注→製造→納入の流れを図式化(図面・設計・製造・出荷)し、ボトルネック工程を特定。
- 図面・設計データ、製造設定データをクラウド/オフサイト保存に切り替え可能か?
- 人材(設計・製造現場)が「この人しかできない」という仕事が無いか?代替できる体制を1つ検討。
- 年1回、訓練・現場確認を行うスケジュールを暫定で決める。
事業を止めない力は、規模の大小ではなく「備える意思」から生まれます。
BCPは“もしもの準備”ではなく、“いつもの強さ”をつくる仕組みです。
いま備えることが、未来の信頼を守り、地域と取引先を支える力になります。
釜屋株式会社は、共に強く、続く企業づくりを応援します。
釜屋オンライン